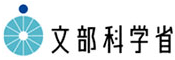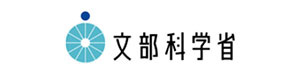国立大学法人福井大学が「実践研究福井ラウンドテーブル2025 Summer Sessions」を開催しEDU-Portニッポン公募事業実施機関から8名の皆さまとEDU-Port事務局から3名が参加しました。福井大学は令和6年度調査研究事業「アフリカ・中東・アジア諸国との連携による新たな教師教育国際協働モデルの構築及びEDU-Portニッポン事業の国内還元に関する省察的調査研究」を実施しています。
「実践研究福井ラウンドテーブル」とは
地域や職種の垣根を越えて教育分野の実践者・実践研究者が集い、少人数のグループに分かれて互いの実践を紹介し合う交流の場で、年に2回開催されています。教育実践者が「限られた時間の中で授業研究をどう進めるか」「すべての子どもたちの可能性をどう引き出すか」といった日々の課題を持ち寄り、他者との対話を通じて省察を深める貴重な機会となっています。2017年からはアフリカの教育関係者も参加して、国際的な実践の共有と対話が活発に行われています。
今回のラウンドテーブルでは、1日目にフォーラム、ポスターセッション、分野(Zone)別の交流が、2日目には小グループで対話をするラウンドテーブルクロスセッションが行われました。就学前教育機関、学校、大学、民間企業等からのべ600名が参加し、活発な交流が行われました。
以下、当日の様子をご紹介します。
-
 ポスターセッションの様子
ポスターセッションの様子 -
 EDU-Port公募事業実施機関間での意見交換の様子
EDU-Port公募事業実施機関間での意見交換の様子
セッションⅠ:教職大学院改革特別フォーラム:教育改革のための国際協働への展望
1日目に開催された教職大学院改革特別フォーラムでは、教育改革に向けた国際的な協働の可能性について、各分野の専門家による発表が行われました。登壇者には、文部科学省大臣官房国際課の大野彰子課長、エジプト教育・技術教育省エジプト日本学校(EJS)のM. Ahmed事業管理部長、そして福井大学大学院連合教職開発研究科の柳沢昌一特命教授が名を連ねました。
大野課長からは「日本型教育の海外展開―現状と展望―」と題して日本型教育の海外展開(EDU-Portニッポン)の現状とこれからについて紹介がありました。
発表後には、東京大学公共政策大学院の鈴木寛教授より「教育改革を推進していくにあたっては、教師や保護者、地域が一体となっていくことが重要」とのコメントが寄せられ、参加者が教育の国際展開に対する理解をさらに深める機会となりました。
ポスターセッション
続くポスターセッションでは、合計14件のポスター発表のうち9件*がEDU-Port公募事業実施機関によるものでした。各発表者より、これまでの活動やその成果が丁寧に紹介されました。発表者には学校関係者のほか、自治体の教育委員会や民間企業も含まれており、教育に関わる多様な視点が紹介されました。また、海外からの参加者との間で活発な質疑応答が行われるなど、国際的かつ実践的な交流の場となりました。
(*福井大学連合教職大学院(2件)、一般社団法人チームがじゃん、大阪府立城東工科高等学校、株式会社公文教育研究会、株式会社すららネット、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン、名古屋経済大学市邨高等学校、ヤマハ株式会社)
EDU-Port公募事業実施機関間での意見交換
ポスターセッションの後、今回のラウンドテーブルに対面で参加したEDU-Port公募事業実施機関関係者が集い、意見交換を行いました。3つのグループに分かれて、EDU-Portに参加したことの意義や海外との交流における難しさ、他機関との協働によるメリット、EDU-Port公募事業実施機関間の連携強化に向けた方策などを議論しました。
セッションⅡ:学校・教育・地域を考える6つのアプローチ
続くセッションⅡは、①学校、②教師教育、③コミュニティ、④International、⑤探究という5つのテーマに分かれて開催されました。各セッションでは、現場の実践に根ざした発表や意見交換が行われました。EDU-Port事務局担当者が参加した④Internationalのセッションでは、冒頭で2名のシンポジスト(Head Teacher, Nalikule College of Education Demonstration School及びActing Deputy Head Teacher, Chiwamba CDSS)がマラウイの授業研究ネットワークに関する事例を紹介しました。その後、さらに4つのグループに分かれて行われたディカッションでは、1つのグループにおいてEDU-Port公募事業実施機関であるヤマハ株式会社大竹悠司氏が、エジプトにおける初等教育への日本型音楽教育導入事業について活動紹介を行いました。
-
 シンポジストによる発表
シンポジストによる発表 -
 ヤマハ株式会社大竹氏による発表
ヤマハ株式会社大竹氏による発表
セッションⅢ:ラウンドテーブルクロスセッション「実践の長い道行きを語り 展開を支える営みを聞き取る」
2日目に行われたラウンドテーブルクロスセッションでは、参加者それぞれが自身の教育実践の経験を持ち寄り、少人数のグループで対話を深めました。EDU-Port公募事業実施機関の参加者も語り手として参加し、これまでの各機関の取組を他者と共有しました。聞き手であった教員等からは「日本の児童・生徒が国際理解を自分事として捉えるためにも、ぜひ出前授業などで詳しい話を子どもたちに聞かせてほしい」、「他国にコンテンツを導入する際の適用方法や学習効果についても知りたい」といった声が聞かれました。
教育実践者が日々の試行錯誤を言葉にし、他者と共有することで、話者自身にとっては実践を再考する貴重な機会となり、聞き手にとっても多様な教育の視点への理解を深める場になりました。異なる立場の人々がそれぞれの視点から対話を重ねることで、教育に対する新たな気づきや共感が生まれていたのが印象的でした。
参加したEDU-Port公募事業実施機関の方からは、「教育実務者・実践者のみなさまと、じっくりと教育の意義やその役割について語り合う時間を通じて、今後の活動にもつながる多くの学びと刺激をいただいた」、「省察するおもしろさと可能性を感じられた有意義な時間だった」といった感想が聞かれました。
2日間にわたる実践研究福井ラウンドテーブルは、多くの参加者の熱意と協力のもと、盛況のうちに閉会しました。国内外の教員をはじめとする教育実践者にEDU-Portについて知ってもらう機会となったとともに、EDU-Portの関係機関間の連携強化につながるアイディアを得るよい機会になりました。