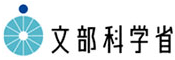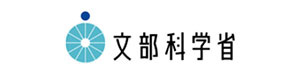1.調査研究の概要
国立大学法人筑波大学は、日本特別活動学会および株式会社パデコと連携し、EDU-Portニッポンの令和5年度調査研究事業として「非認知能力の育成に向けた特別活動の国際化と質保証に関する研究~日本型教育先進地エジプトにおけるTokkatsuの効果検証~」を実施しました。本事業では、エジプトで導入・実施されているTokkatsuの現地化の実態を調査し、個人と社会のウェルビーイングを支える要素ともいわれる非認知能力に与える影響を定性的に検討しました。さらに、エジプトの関係者と共同で、質保証制度を開発することを通じて、国際的通用性と倫理性を備えた日本型教育モデルの発展を目指してきました。
2023年12月と2024年12月の2回にわたる現地調査では、日本型教育を導入するエジプト日本学校(EJS)、公立の一般校、カイロ日本人学校(CJS)などを訪問し、学級活動を参与観察するとともに、児童、教師、Tokkatsuの指導員であるTokkatsu Officer (TO)に対してインタビューを行いました。これらの結果を分析し、国内・国際学会で合計16件の研究発表を行っています。詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://tokkatsu-eduport.education.tsukuba.ac.jp/
ここでは、2025年2月1日に開催した成果報告会(対面・オンライン合わせて参加者119名)の内容を中心に、2年間の活動概要と今後の展望を紹介します。
(報告会の資料はEDU-Portニッポンのウェブサイト「プロジェクトの成果を検索する」のページでご覧になれます。
https://www.eduport.mext.go.jp/result/20240306-9785/)
2.調査研究を通して明らかになったこと
(1)小学校における非認知能力育成の効果検証
2023年に参与観察したEJSの学級会を2019年の学級会動画と比較したところ、教師の発言割合が低下し、「教師が動かして教師が決める学級会」から「児童が動いて児童が決める学級会」になっていることがわかりました。また、児童同士の発言がつながるようになり、「個々の児童が自分の思いを主張する学級会」から「人の話をよく聞いて、その思いを受けて発言する学級会」へ進化していることも明らかになりました。
発話記録の分析では、2019年は議論が進んだり戻ったりする傾向があり、全体から切り離された発話が散見されました。それに対して2023年は、まとまりのある発話が重層的に積み重なる構造となり、1つの提案について吟味して意見を取捨選択する形がみられました。このように5年間で学級会の構造は驚くほど変化しましたが、一方で提案のしぼりこみと合意形成プロセスについては課題が見られました。
EJSの教師、保護者、TOを対象とした参加型評価ワークショップでは、Tokkatsu が与えた最も重大な変化として、子どもが自由に表現し、チームワークを尊重し、問題を探究して解決できるようになったことがあげられました。さらに、協力的になり、他者や違いを受け入れ、リーダーシップや責任感を身につけたことで自己肯定感が高まり、自信をもつようになったことも語られました。その背景には教師の変化があり、個性に配慮した子ども中心の授業への変容や、同僚性の高まりを活かした授業改善と職能発達が確認されました。
-
 EJSにおける学級会の参与観察
EJSにおける学級会の参与観察 -
 EJSにおける参加型評価ワークショップ
EJSにおける参加型評価ワークショップ
(2)Tokkatsuの受容と現地化プロセスの解明
Tokkatsuの導入・普及の要因について、インタビューに基づき、受信側であるエジプト(内因)と発信側である日本(外因)、それぞれの促進要因と阻害要因を明らかにしました。導入については、内因・外因ともに促進が阻害を上回っていましたが、とりわけ国家的次元の内因(エジプト国内の社会的要因)の強さが目立ちました。普及に関しては、教育文化的次元の考察から、宗教的基盤をもたないTokkatsuが、イスラム教の理念を実生活で体現する教育に近いと解釈され、実践が積み重ねられたことが示されました。教師主導型の教育文化はTokkatsu普及の内的な阻害要因でしたが、そこからの「変化の手ごたえ」が促進要因として作用しました。つまり、教育を含めたエジプトの文化に内在化していた価値が、Tokkatsu導入をきっかけに顕在化したという見方ができます。既存文化との整合性を保った形での教育モデルの受容と現地化は、海外展開における倫理性の確保につながる可能性があります。

TOへのインタビュー
(3)持続性強化に向けた質保証制度の共同開発
Tokkatsuディプロマ・プログラムの設置に関してエジプト側と協議し、養成コース概要を作成しました。エジプト高等教育省の大学設置審議会の教育学部委員会で承認され、現在はプログラムの運用に向けた検討が進められています。
また、エジプト人研究者と共同で、優秀なTOを認証するTokkatsu研修・認証制度(TTCS)の改善に取り組みました。最終面接試験の評価基準は、誰がやっても同じような結果になることが多く、Tokkatsuの未経験者でも評価しやすい一方、定性的な見方はできないデメリットがあります。評価者の質をどう高めていくか、及び認証を受けることのインセンティブを確保することが、今後の課題として示されました。
(4)日本人学校と現地校の協働のモデル化
EJSとカイロ日本人学校(CJS)の教師による合同模擬学級会のデータ分析、およびインタビュー調査から、日本人学校と現地校の連携の在り方を検討しました。多くの日本人学校は、その使命として現地理解教育を推進します。しかし、教師間の交流は、児童生徒の交流を目的とする交流に限定されることが多く、教育課程の違いやその国ならではの学びについて、掘り下げることができていません。その点では、Tokkatsuという共通の教育課程を対象としたEJSとCJSの授業研究を通した交流は、新たな可能性を提示しています。協働を通して、異国の教育課程をより深く理解し、日本の教育課程のよさを伝えるとともに、そこから日本型教育の意義を再評価していくことが必要です。
-
 TTCS最終試験(TOによる教師へのフィードバック)
TTCS最終試験(TOによる教師へのフィードバック) -
 CJSとEJSによる合同模擬学級会
CJSとEJSによる合同模擬学級会
(5)エジプトに学ぶ日本の学級会の授業改善
児童の自由な発想を生かしつつ、粘り強く合意を得ようとするエジプトの学級会のよさを生かして、日本で学級会の研究授業を行いました。具体的な手立ては、①議題を学級経営・学級目標に意図的に結び付けずに、児童がやりたいことを議題にする、②提案理由を事前に文章として作って読み上げることをやめる、③全員一致を目指した話合いを行う、というものです。授業後の質問紙調査では、従来の学級会とは違うと感じた児童は76%、多数決で決めるのはよくないと思う児童は72%、全員一致(合意形成)で決めるのがよいと思う児童は96%、学級会が学級の成長につながっていると思う児童は100%でした。
3.日本の特別活動に対する示唆
エジプトではTokkatsuの目的を常に確認しながら、活動を実践していました。それに対して日本では、特別活動が当たり前であるがゆえに、目的が曖昧であったり手段と混合されたりといった事態が起きているように思います。改めて、活動ありきでなく、何のための特別活動なのかを意識することの重要性に気付かされました。
学級会の授業改善プロジェクトでは、日本型教育のさらなる国際化に向けた手がかりを得られました。エジプトの学級会では、よくも悪くも話合いの「枠」がしっかりしていません。柔軟な「枠」であるがゆえに混乱もありますが、真心を尽くして他の児童に説明することで、「枠」自体を自分たちで乗り越えていく様子が見られました。このことから、子どもの自治的活動の範囲を広げ、教師の適切な指導の範囲を狭めていくことが、日本の課題であると認識しました。
さらに、特別活動の質保証制度という点では、エジプトは日本に先行しています。日本では特別活動を主担当とする指導主事が教育委員会事務局に配置されていないことも少なくなく、またその指導能力にばらつきがあります。研修等を通して、学校現場を支援する指導主事の専門性の向上を図っていく必要があります。
4.今後の活動の展望
本事業を通して、Tokkatsuを導入している国々がつながり、互いに学び合うことが日本型教育のさらなる国際化に寄与すると考えるに至りました。今後は、エジプトだけでなく他国も巻き込み、Tokkatsuに関わる実践者・研究者が学び合う国際ネットワークを作っていきたいです。さらに、このネットワークを活用して、ローカルとグローバルの両方を視野に入れた教員養成・研修プログラムと、それを持続的に評価・改善していくシステムを開発できないか模索しています。